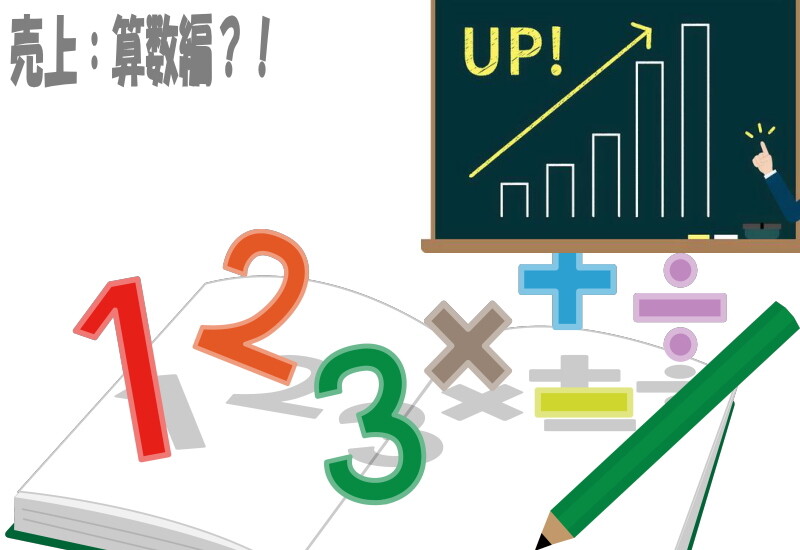ソーセージの歴史と種類

ソーセージの歴史は
その起源は、はっきりしていませんが、3000~3500年くらい前から始まっているようです。
というのも、3500年くらい前にエジプトやバビロニア地方でソーセージのようなん物が食べられていたという
話がいくつも残っているからです。
また、紀元前のギリシャの叙事詩には祝宴の食材としてソーセージらしきものが登場しているようです。
その最も古い種類は血のソーセージ、つまりドイツでブルートヴルスト(Blutwurst)と呼ばれているもので、
ホメロスの『オデュッセイア』には、「脂身と血を詰めた山羊の胃袋」などといった記述も残されています。
ローマ時代には種類も増え、しかも焼くだけでなく、茹でるものも現れます、有名なアピキウスの料理書にもソーセージの作り方が載っており、古代ローマ人は、ソーセージを非常に愛し、お祭りに出されるほどでした。
ところが、ローマ皇帝(コンスタンティヌス帝)が、そのソーセージを贅沢だと「ソーセージ禁止令」を出すという事件?が起こりました。
しかし、人々のソーセージ愛は、その命令を勝り、密造が蔓延したため、結局はこの禁止令は廃止されました。
そしてその後は、更にソーセージ作りが盛んになっていったようです。ローマ人にとってのソーセージは、デリカテッセン(惣菜のようなもの)であったかもしれません。
ソーセージという名前の語源は、「salsus」(塩漬けして貯蔵された肉、を意味するラテン語)からきていると言われています。
ところで、日本ではどうだったのでしょうか。
日本では、他の国と違って、ハム文化よりソーセージ文化が広まるのが遅かったようです。
日本ではじめてソーセージを食べたと言われているのが、1860年の第1回遣米使節メンバーであったと言われていますが、
実際に、ソーセージの製造技術が日本に伝えられたのは、大正時代、第一次世界大戦時であったようです。
捕虜となったドイツ人の中にいたソーセージ製造技術を持った人たちで、現在は、店名やブランド名にもなっている、ローマイヤー、カールレイモン、ヘルマンウォルシュケ、バンホーデン、ブッチングハウスなどの技術者です。そこから、現在の日本、食肉加工品の販売額ダントツトップのソーセージの発展が始まったわけですね。
とはいっても、一般に広まったのは昭和30年代以降で、歴史は浅い?といっても良いでしょう。
ソーセージの作り方
ブロックの豚肉や牛肉などを整形(原料のお肉を脂やスジをとり、用途別に整形し分けます)
↓
肉挽き(原料となる肉類をチョッパー:ひき肉機でひき肉にします)
↓
塩せき(原料肉に塩せき剤:塩や発色剤など、を加えて冷蔵で熟成します)・・・この工程のないものもあります。
↓
混合調味(それぞれに香辛料や調味料を使い、独自の味付けをします)
↓
充てん(ケーシングに詰めてそれぞれのかたちに整えます)
↓
乾燥くん煙(煙でいぶし、保存性を高め、色目と香りをつけます。くん煙は行わない場合もあります)
↓
蒸煮(くん煙だけでは、加熱が十分ではないので、お湯や蒸気を使い肉の中心部まで加熱します)
↓
冷却(急速冷凍をかけ、肉質の引き締めと、細菌の増殖を防ぎます)
この後は、商品別・用途別に包装をされ、検査を受けて出荷を待ちます。

ソーセージの種類、JAS法の分類による
ボロニアソーセージ(熟成)、フランクフルトソーセージ(熟成)、ウインナーソーセージ(熟成)、リオナソーセージ、
レバーソーセージ、レバーペースト、セミドライソーセージ、ドライソーセージ、加圧加熱ソーセージ、無塩せきソーセージ、混合ソーセージとなります。
・ボロニアソーセージ(熟成)・・・上記のような作り方(通常の作り方)で、豚、牛、鶏等をミンチにして、太さは最大級の牛腸に詰めた物。人工ケーシングの場合、36mm以上のものです。
(イタリアのボロニアの代表的なソーセージであることから「ボロニアソーセージ」といわれる)
・フランクフルトソーセージ(熟成)・・・製法は通常の作り方ですが、豚腸または同じ位の太さのケーシング(太さ20~36mm未満)に詰めたものです。
・ウインナーソーセージ(熟成)・・・製法は通常の作り方ですが、羊腸または同じ位の太さのケーシング(太さ20mm未満)に詰めたものです。
・リオナソーセージ・・・製法は通常の作り方ですが、チーズ、ほうれん草等の野菜を具として混ぜたソーセージのことです。
・レバーソーセージ・・・製法は通常の作り方ですが、豚、牛、鶏等の肝臓のみを使用(原材料にしめる割合を50%未満におさえ)して混ぜたソーセージのことです。
・レバーペースト・・・製法は通常の作り方ですが、豚、牛、鶏等の肝臓のみを使用(原材料にしめる割合を50%を超えて)して混ぜたソーセージのことです。
・セミドライソーセージ・・・製法は通常の作り方ですが、水分が55%以下に乾燥させて仕上げたソーセージのことです(ドライソーセージは除きます)。
・ドライソーセージ・・・有名なのが、サラミソーセージですが、豚か牛がメインで、調味してから充てんし、乾燥させて仕上げたソーセージのことです(加熱しず乾燥させ、水分が35%以下のもの)。
・加圧加熱ソーセージ・・・製法は通常の作り方ですが、120℃で4分間加圧して加熱して仕上げたソーセージで保存性に優れています。
・無塩せきソーセージ・・・製法は通常の作り方の流れですが、塩せきはしないで仕上げたソーセージです。
・混合ソーセージ・・・製法は通常の作り方ですが、畜肉を主原料に、魚肉を加えたソーセージです(魚肉類の割合が15~50%未満)。
種類が豊富に揃っていますね。